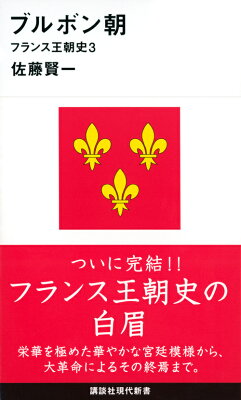どうも、りきぞうです。
大学院では、キャリア論と社会保障を研究していました。
社会人なってからは、[予備校講師 → ウェブディレクター → ライター]と、いろんな職業にたずさわってきました。
働き方についても、[契約社員 → 正社員 → フリーランス]と、ひと通り経験してきました。
働くなかで思うのは、自分の市場価値をアップするには「教養」が大切だということ。
・発想がすごいなぁ
と、思う人は、キホン、教養を身につけています。
なかでも、重要なのは「世界史」です。
ここ数年、ビジネスマンの必須知識として「世界史」が注目をあつめています。
ネット時代をむかえ、グローバル化が加速しているからです。
とくに、世界史をまなぶうえで、フランスの歴史は、必須です。
ヨーロッパ史において、フランスは、いつでもメイン・プレイヤーだからです。
とはいえ、フランスの歴史は、なかなかとらえてにくい。
そんなとき、つぎの本をみつめました。
著者は、フランス研究の第一人者 ─ 。
この本では、近世フランス・「ブルボン朝」のながれをたどっていきます。
小説家でもあるため、文体にドライブ感があります。
物語のように、ぐいぐい読みすすめていけます。
近世のフランス史を知るには、もってこい1冊です。
…
また本書は、『フランス王朝』シリーズの第3巻にあたります。
3冊とおしでみると、中世初期〜近代初期のフランス史を、ざっくり把握できます。
…
ちなみに、わたしは、Kindle 版で読みました。
以下、引用番号は、こちらの本によります。
目次
佐藤賢一『ヴァロワ朝 フランス王朝史2』の概要
まずは、目次。
こんなかんじです。
第1章 大王アンリ4世(1589年〜1610年)
第2章 正義王ルイ13世(1610年〜1643年)
第3章 太陽王ルイ14世(1643年〜1715年)
第4章 最愛王ルイ15世(1715年〜1774年)
第5章 ルイ16世(1774年〜1792年)
第6章 最後の王たち
おわりに
フランスは、[カペー朝 → ヴァロワ朝]とつづき、さいごは、ブルボン朝がおさめることになります。
歴代の国王をたどることで、フランス史のながれをみていきます。
キホン物語調になっているので、順々で読んでいくのが、おすすめです。
佐藤賢一『ブルボン朝 フランス王朝史3』の詳細
以下、気になるトコをあげていきます。
ポイントは、つぎのとおり。
- ブルボン家は末端の家系
- リシュリューの政治運営
- ルイ14世の国家戦略
以下、ひとつひとつ、みていきます。
ブルボン家は末端の家系
フランスは、それまで[カペー朝 → ヴァロワ朝]とつづいてきました。
国王の座には、直系(本家)の男子がついてきました。
しかし、ヴァロワ朝・断絶後、あとをついだのは、分家の分家である、ブルボン家でした。
カペー王朝から分かれたのは、なんと十代も遡る三百年前だ。それもフランス王家の分家のブルボン公家から、さらに分かれた分家のラ・マルシュ伯家、そこから再び分かれたヴァンドーム伯家の流れなのであり、要するに末端の家系である。(no.95)
ブルボン家ときくと、華やかなイメージがあり、伝統ある家系と思います。
けれど、王国をひきついだときには、末端の家系とみられていました。
これは意外ですね。
リシュリューの政治運営
ブルボン朝をとおしでみるとき、歴代の王たちは、宰相に恵まれていた、とわかります。
そのうちのひとりが、リシュリューです。
司祭だったかれは、ルイ13世の「右腕」として活躍しました。
おもしろいのが、もともとはルイの母「マリー」に抜擢されて、政界に入ったこと。
しかし、母と息子が対立 ─ 。
するといつのまにか、息子に重宝されるようになり、ルイ13世の味方にまわります。
さいごは母を追放するかたちで、リシュリューは中央にとどまりました。
本書では、母が息子に残した最大のプレゼントが、リシュリューだと皮肉っています。
リシュリューこそ母マリー・ドゥ・メディシスが息子のルイ十三世に与えた、唯一にして最大の贈り物だったと、そこは異論の余地がないところである。
〝一寸先は闇〟のフランス政治 ─ 。
リシュリューの立ちまわり or 交渉力が、なんとなく透けてみえます。
◇ 国家理性の自覚
事実上、フランスの国家運営をおこなうことになったリシュリュー ─ 。
かれは司祭にもかかわらず、現実政治(リアル・ポリティクス)のスタンスをとります。
当時、ヨーロッパには、宗教対立がおきていました。
vs.
・プロテスタント(=ユグノー)
です。
フランスは、対外上、「カトリック」の立場をとっていました。
そのなかで、ルイ13の妹「アンリエット」と、イギリスの「チャールズ1世」の結婚をきめます。
イギリスは、プロテスタントの国でした。
にもかかわらず、結婚=同盟をむすびます。
5月11日にはアンリエット王女とイギリス王チャールズ一世の結婚が決まった。フランスはイギリスと同盟を結ぶということだ。が、そのイギリスはプロテスタントの国である。縁談を進めたのはルイ十三世だが、もちろん新宰相の賛同あっての話だ。そのリシュリューは枢機卿で、つまりはカトリックの高位聖職者である。(no.1568)
なぜか。
それは、宗教の考えよりも、国家の利益を重視していたからです。
本人は司祭で、フランスはカトリックなのに、イギリスとの〝ウィンウィン・カンケー〟をだいじにして、あえて同盟をむすびました。
というのも、フランスをはさむように、「カトリック」のハプスブルク家が、勢力をのばしていたからです。
外ではフランスを東西から挟みつけるようなハプスブルク家の覇権を、崩さなければならなかった。それがカトリックであるならば、プロテスタントを措いて他には肩入れできない。しごく明快かつ大胆不敵な論理において、その外交は水面下で進められていた。(no.1795)
そこで、「プロテスタント」のイギリスと手をむすびました。
つまり、かれは「国家理性」のもと、政治をおこなっていたわけです。
なにがおもしろいって、リシュリューはまがりなりにも、教会ではたらいていたこと。
「政治と宗教は、別だよ」 ─ そう考えていたわけです。
故アンリ四世と同じで、優先するのは宗教ではなかった。今や「国家理性(raison d’Etat)」がはっきりと意識される。まずもっての大事は国益であり、全てはフランスのために行うというのが、リシュリューの考え方なのである。(no.1568)
フランス王家は国内ではプロテスタントを討伐したが、国外で応援していたのはプロテスタント勢力だった。宗教は関係ない。リシュリューの考え方は一貫していた。大事はフランス王国の安泰と繁栄なのである。(no.1795)
アンタンダン制度の整備
リシュリューは、王家のため、内政改革にも、とりかかります。
そのひとつが、アンタンダン制度の整備です。
それまで地方政治は、その土地の有力者にまかされていました。
たとえ中央から役職を与えれたとしても、その「肩書き」が、売り買いされていました。
つまり、お金さえあれば、どうにでもできる状態だったわけです。
この事態を改善するため、リシュリューは、「アンタンダン」という役回りを強化します。
アンタンダンとは、委任官僚のことです。
期限付きの地方官で、国王はいつでも、任命・免責できます。
そのため、かれらを利用するかたちで、国王のおもいどおりに、地方各地を統治することができました。
アンタンダンは違う。王の委任を受けただけの、委任官僚(commissaire)だからだ。一時的、限定的な権限を与えるものなので、王は随意に任免することができるのだ。官職を買い戻さなければ解雇できない官僚、いうところの保有官僚(officier)と区別される所以で、これに比べた委任官僚であるアンタンダンは、文字通り王の手足としてしか働けない形なのだ。ならば使わない手はない。(no.1741)
リシュリューは、全国各地に配置することで、地方にたいする中央の〝しばり〟をきつくしました。
それにより、いっそう国王にたいする権力集中を高めつつ、地方勢力の台頭をおさえこもうとしたわけです。
常に目を光らせていたら、どうなるか。州総督の州行政を常に監督、ときに処断にまで及んだら、どうなるか。財務行政に介入して、その公正化を図ったら、どうなるか。地方が中央から分離して、反乱の基盤になるような事態は起こりにくくなる。州総督たちも鳴りを潜めざるをえなくなる。(no.1756)
具体的には、(タイユ税など)各地の地主・民衆にたいする徴税を、アンタンダンに任せることになりました。
アンタンダン経由で、ブルボン家の財政基盤を強化しようしたわけです。
決定的だったのが1642年2月の勅令で、在地における財政業務はタイユ税も、タイヨン新税も、追加分も、軍隊の補給徴発に関しても、その割当のみならず徴税についても、全てアンタンダンに委任されることになった。他は出納官も、エリュも、タイユ徴税官も、全てアンタンダンに従えられる立場となった。法律的にも管区に常駐する常設の役職になり、こと財務に関しては、アンタンダンこそ行政の主体となったのである。(no.1766)
ルイ14世の国家戦略
リシュリュー&ルイ13世が亡くなったあと、国王をひきついだのが、ルイ14世でした。
リシュリューが任命した、宰相「マザラン」のもと、政治をおこないます。
知っているとおり、ヴェルサイユ宮殿をつくるくらいですから、いかに豪華なくらしをしていたかがわかります。
それもこれも、リシュリューの財政改革のおかげだといえます。
お金がたくさんあるので、ルイ14世は、他国に戦争をたくさんしかけました。
けれどそれ以上に、文化・建築にも力をいれます。
なぜでしょうか。
これも地方勢力をおさえるための戦略でした。
中央の文化を光らせることで、相対的に、地方の魅力を下げるねらいがありました。
つまり、いまでいうところのブランド戦略です。
地方にいるのは「ダサい」─ 。
中央(パリ)においてこそ、人生において、見るべきものがある ─ 。
そう印象づけたわけです。
そこにあるのは文化だった。全てにおいて最高度に洗練された、まさしく究極の文化である。それを持つのがルイ十四世だからこそ、このフランス王に近づきたがる。それがあるのがヴェルサイユだからこそ、誰もがこぞって行きたがる。それというのも、他は素敵でないからだ。あるいは魅力をなくしたからだ。(no.2674)
つまり、武力でおさえこむよりも、文化で〝地方の価値を失くす戦略〟をとったわけです。
地方に構えて、なにが偉い。今や難航不落の要塞に籠もるより、ヴェルサイユ宮殿に小さなアパルトマンを与えられるほうが、何倍も羨ましがられる。鉄砲、大砲に通暁して、なにが偉い。今やモリエールの喜劇、ラシーヌの悲劇と文学を語れるほうが、遥かに皆に尊敬される。(no.2673)
今や注目されたければ、羊毛の鬘と絹の靴下だ。難攻不落の城塞を落としても、なんの自慢にもならない。美しい伯爵夫人を落としたほうが、どれだけ世の喝采を浴びることか。血と火薬の臭いが身体に沁みついているなど言語道断で、一端の顔をしたいのなら白粉と香水を常に肌から薄ら 燻らせることなのだ。そうやって、ヴェルサイユの価値が他を 凌駕 した。起きていたのは、武から文への転換だった。(no.2691)
暴力から文化へのシフト ─ これこそ「絶対王政」の本質でした。
絶対王政ときくと、国王が〝好き勝手〟な政治をやっていたイメージがあります。
もちろんそれも事実です。
けれどそれ以上に、全国の民衆にたいして、
・ブランドでもって、あこがれを抱かせる
こうすることで、権力を高めていったわけです。
フランスの栄光を高めるために、王はフランスの文化を高め、それを自らに集める。フランスには息を呑むばかりに豪華な建物がある。フランスには恍惚となるような芸術がある。面白い文学も、最先端の学問も、美味しい食事も、憧れのファッションも、まさに魂を奪われるような文化が、これでもかとフランスには満ちている。ヴェルサイユ宮殿を一目瞭然わかりやすい広告塔に用いながら、ルイ14世は、フランス人でよかった、ああ、こんな素晴らしい国に生まれてよかったと、フランスに暮らす人々に思わせたのだ。(no.2768)
じじつ、ルイ14世時代のヴェルサイユ宮殿は、出入り自由でした。
一般の人たちも、わりと気軽に、建物を見物することができました。
こうすることで、
↓
地元にもどって、ルイ14世の威信をつたえる
↓
地方が、中央のチカラをあおぎみる
といった、サイクルがうまれるわけです。
つまり、ルイ14世の趣味というだけでなく、文化政策は、広告事業の役割もあったわけです。
ヴェルサイユは広く開放されていた。少し意外に感じられるが、基本的には誰もが出入り自由だった。この光り輝くような世界を覗きみることは、誰に禁じられたわけでもなかったのだ。フランス全土から人が集まる。故郷に帰れば、ヴェルサイユの土産話をしないではいられない。フランス王の宮殿は素晴らしかったと伝えないではいられない。フランスは素晴らしい国なのだと誇らないではいられない。 〔……〕かくて意識的中央集権化を図ることで、フランス王はフランスという国の中身を、地理的中央集権化に近づけていく。(no.2768)
武力・暴力ではなく、文化・芸術でもって、中央集権化をはかる ─ 。
これがルイ14世の政治戦略でした。
おわりに
本書は、ブルボン朝の視点から、フランス史のながれを、コンパクトにまとめています。
物語調で、すらすらよめます。
ざっくりと、フランスの歴史を知るには、役立つ1冊です。
よければ、チェックしてください。
ではまた〜。