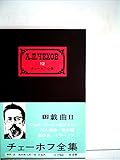どうも、コント作家のりきぞうです。
きょうも、コント作品をレビューしていきます。
取りあげるのは、チェーホフ『イワーノフ ─ 戯曲』。
中期の作品です。
1889年1月31日に初披露されました。
さいしょは、1887年に喜劇として書かれました。
しかし観客の評価はいまいちで、そのあとチェーホフ自身があらためて「ドラマ」として作りなおしました。
今回は、こちらを取りあげます。
以下、ストーリーの大枠をみたあと、笑いのポイントをあげていきます。
ちなみに、神西訳で読みました。
以下、引用のページ番号は、うえの文献によります。
また、松下裕さんの訳もあります。
こちらのほうが読みやすいかもです。
よければチェックしてみてください。
目次
ストーリーの大まかな流れ
人物
イワーノフ
アンナ……イワーノフの妻
シャベーリスキイ……イワーノフの叔父、同居人
ボールキン……同居人
レーベヂェフ……地方議員
サーシャ……レーベヂェフのむすめ
場所
ロシア中部
あらすじ
農民委員の役員イワーノフ。
地位も高く、まえは裕福だったが、いまは借金に追われている。
気分もウツっぽく、なにもやる気がおきない。
家には、妻アンナ、叔父シャベーリスキイ、領地の管理人ボールキンが暮らしているが、それぞれが彼を苦しめる。
アンナは、結婚当初のように愛してくれないとののしる。
シャベーリスキイは、クソまじめなイワーノフの性格をバカにする。
ボールキンは、いつも儲けばなしを口にして、イワーノフから小銭をせびる。
彼のユウウツは日を追うごとに増していく。
そんななか、地域の名士レーベヂェフの家でパーティーが開かれる。
招待をうけるイワーノフだったが、足どりはおもい。というのも、レーベヂェフの妻ジナイーダに借金をしているため。
お金がなく、返済の延期を頼まないといけない。
イワーノフのつらさを感じない三人は、「自分たちも連れていけ」と非難する。
肺病のため、医者から外出を止められている妻のアンナは、レーベヂェフのむすめサーシャとの浮気をうたがい、自分も行くとダダをこねる。
ますますユウウツになるイワーノフ。
ジナイーダにも返済の延期を断られ、なにもやる気がおきなくなる。
しかしそんななか、妻の予感どおり、むすめのサーシャがイワーノフに告白してきて……。

ひとこと
ストーリーだけみれば、シリアスな演劇のようにみえます。
じっさい発表当初から、イワーノフは、ウツやメランコリーにくるしむ人物として扱われてきました。
イワーノフ 〔同居するシャベーリスキイ & ボールキンについて〕余計者のむれ、余計なことば、バカげた質問にたいする返事の必要 ─ こうしたいっさいが(……)ぼくを苦しめるんです。
(p.11)
また、他人に共感できない、虚無感(ニヒリズム)におちいる主人公だとも。
イワーノフ (……)あれは相変わらず、ぼくを愛しているのに、ほくは……(両手を広げる)きみはいま、あれが近いうちに死ぬと言われた。それでもぼくは愛も哀れみも感じないで、なにかこう空虚さ、倦怠を感じるだけなんです。
(p.13)
たしかにネガティブな性格にはまちがいありませんが、、いつでもどこでも、ウツの症状を口にするのは、こっけいにうつります。
その意味で、やはりこれは「喜劇」であり、笑いばなしです。
そもそもチェーホフは、この作品を「喜劇」として書きました。
虚無や倦怠をネタに、笑いをとろうとしているのは、あきらかです。
過剰なほど「ユウウツ」をアピールし、非難されようが心配されようが、告白されようが愛されようが、まわりの反応がプラスでもマイナスでも、同じように「空虚さ」を訴えます。
この「いっぺんとう」な性格が笑いをさそいます。
レーベチェフ (……)この郡内でのきみの悪口は、いまにもきみのところに検事がたずねてきそうなほどだ……きみは、人殺しとも、吸血鬼とも、追いはぎとも言われている。
イワーノフ みんなバカげたことですよ。それより、ぼくは頭が痛い!
レーベチェフ あんまり考えすぎるからさ。
イワーノフ ぼくはなにも考えていない。
(p.58)
笑いのポイント
笑いのポイントをみていきます。
コントや喜劇で大事なのは、キャラクターとプロット。
この作品ではプロットに注目してみます。
コントのプロットはとてもシンプル。
[設定 → 展開 → オチ]がキホンのながれ。
 コントの書き方 ─ プロットの構成について
コントの書き方 ─ プロットの構成について
なかでも「展開」が、作品の良し悪しを決めるんだけど、これにも「型」があります。
パターンは「反転」「逆転」「交錯」の3つです。
 コントの書き方 ─ プロットの展開について
コントの書き方 ─ プロットの展開について
ストーリーを整理してみると、この作品は「反復」の構図をとっているわかる。
「反復」では、状況や環境が変わっても、それまでと同じアクション、セリフ、出来事をくりかえすようすを描きます。
それによって笑いを引きおこします。
この作品でも、倦怠と空虚におちいるイワーノフが、のべつ「ユウウツ」を口にする。
同情するレーベヂェフから心配されても、キモチを察してくれない同居人たちから非難されても、同じように「自分の無意味さ」をアピールする。
このくりかえしが笑いを引きおこす。
図にするとこんな感じ。
・「クソまじめ」とバカにされる
・「愛してほしい」とののしられる
・借金を心配される
・告白される
イワーノフ = ウツを訴える
にしても、どうしてチェーホフが「ふさぎ虫」を主人公したのか?
それは、この時代の雰囲気を感じとっていたから、と考えられます。
年配のレーベヂェフが、若者をみたときの評価が、それをものがたっています。
レーベチェフ 近ごろの青年は(……)なんだねありゃ。不景気で、茹ですぎたフヌケばかりだ。おどりっぷりも、はなしっぷりも、飲みっぷりもなっとらん。
(p.29)
もちろんレーベヂェフと同じ世代の人たちも「退屈」「倦怠」に苦しんでいるが、とくに若い人は、その雰囲気をイチバンに感じている。
なんだかいまの時代に、よく似ている気がしますね。
テーマとして、チェーホフ作品は、ますます読まれていくような気がします。
まとめ
こんなふうに、プロットに注目してみていくと、よりいっそうコントを楽しめます。
ほかの作品でも、こんな視点に立って作品で観ています。ちがう記事ものぞいてみてください。
ではまた。
よきコントライフを〜。