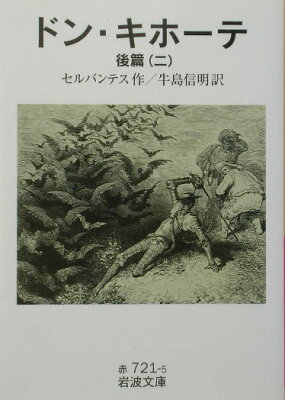どうも、りきぞう(@rikizoamaya)です。
大学院では、キャリア論と社会保障を研究していました。
社会人なってからは、予備校講師 → ウェブディレクター → ライターと、いろんな職業にたずさわってきました。
働き方についても、契約社員 → 正社員 → フリーランスと、ひと通り経験してきました。
働くなかで思うのは、自分の市場価値をアップするには「教養」が大切だということ。
・深くものごとを考えられる
こういう人たちは、キホン、教養を身につけています。
教養とは、なにか ─ それは、歴史と古典です。
なかでも、文学作品の古典は、王道といえます。
わたしも、計300冊以上は、読んできました。
きょうは、
を紹介していきます。
まえに、「前編」を紹介しました。
 セルバンテス『ドン・キホーテ 前編』感想&レビューです。
セルバンテス『ドン・キホーテ 前編』感想&レビューです。
きょうは、そのつづきです。
近代以降の作家は、たいてい『ドン・キホーテ』の影響をうけています。
小説のカタチをつくったといってもよい。
それくらい、重要な作家であり、作品です。
なので、近世・近代以降の古典文学にふれるには、まずは『ドン・キホーテ』から入るのがベターです。
ちなみに、セルバンテスの人物像・著書については、前編のほうで書きました。
基本情報を知りたい方は、そちらをチェックしてみてください。
目次
セルバンテス『ドン・キホーテ・後編』の概要
前編と同じく、後編も長いです。
文庫本で、3冊分あります。
出版時期をみると、前編の10年後に後編が書かれました。
構想&執筆期間を長くとり、これだけの分量になったんだと思います。
後編も、貧乏地主「キハーノ」が、遍歴・冒険をする内容です。
「騎士道物語」を読みすぎて、自分が「ホンモノの騎士」だと思いこみ、物語 / 現実の区別ができなくなる点は、同じモチーフです。
ただ、前編のちがうのは、まわりの反応・行動です。
すでに「ドン・キホーテ」の存在が、スペインじゅうに知りわたり、周囲の人たちは、かれを「狂人」としてあつかいます。
(ちなみに、認知されている理由は、10年前に出版された「前編」が売れたから。じっさいに「売れた」という事実を、後編のストーリーに折り込み、利用します。セルバンテス・お得意の「メタ手法」です。)
さらに、変わり者のドン・キホーテに、〝ドッキリ〟をしかけ、笑おう・楽しもうとする連中まであらわれます。
なので後編は、ドン・キホーテが「狂気」を発揮するというより、「狂気」を利用され、笑われるかんじがつよいです。
つぎに目次。
後編は、74章で構成されます。
前編は、「部(セクション)」がついてましたが、後編はありません。
牛島訳の各巻では、つぎの章が収録されています。(※ タップすると、開きます)
第2章 サンチョ・パンサがドン・キホーテの姪と家政婦を相手に展開した瞠目に値する口論、およびそのほかの愉快な出来事を扱う章
第3章 ドン・キホーテとサンチョ・パンサと学士サンソン・カラスコのあいだに交わされた 滑稽 な会話について
第4章 ここではサンチョ・パンサが、学士サンソン・カラスコの質問に答えてその疑念を晴らすと同時に、そのほかの知るにも語るにも値することが述べられる
第5章 サンチョ・パンサとその妻テレサ・パンサのあいだに交わされた賢くも滑稽な会話、および、思い出すだに愉快なことについて
第6章 ドン・キホーテとその姪および家政婦とのあいだに起こったことを扱うが、これは物語全体のなかで最も重要な章のひとつである
第7章 ドン・キホーテとその従士のあいだに起こったこと、ならびにそのほかのめざましい出来事について
第8章 ここでは、思い姫ドゥルシネーア・デル・トボーソに会いにいくドン・キホーテに起こったことが語られる
第9章 ここでは、この章で明らかになることが語られる
第10章 ここではサンチョがドゥルシネーアを魔法にかけるのに用いた策略、ならびにそのほかの真実であるがゆえになおさら滑稽な出来事が語られる
第11章 荷車に乗った《死の宮廷》一座と勇敢なドン・キホーテとのあいだに起こった奇怪な出来事について
第12章 勇敢なドン・キホーテと大胆不敵な《鏡の騎士》とのあいだに起こった異様な冒険について
第13章 ここでは《森の騎士》との冒険の一環として、二人の従士のあいだに交わされた、新奇にして分別のある、穏やかな会話が扱われる
第14章 ここでは《森の騎士》の冒険が続けられる
第15章 ここでは《鏡の騎士》とその従士が何者であったかが語られ、彼らのことが明かされる
第16章 ドン・キホーテとラ・マンチャの賢明な紳士とのやりとりについて
第17章 ここではドン・キホーテの前代未聞の豪胆さが到達した最高の点、あるいは到達しえた極限が明らかにされ、と同時に上首尾に終ったライオンの冒険が語られる
第18章 《緑色外套の騎士》の家、あるいは城においてドン・キホーテに起こったこと、および、そのほかの風変りなことについて
第19章 ここでは恋に悩む羊飼いの冒険、ならびに、実に愉快なそのほかの出来事が語られる
第20章 ここでは長者カマーチョの婚礼と貧者バシリオの冒険が語られる
第21章 ここではひきつづきカマーチョの婚礼が、そのほかの楽しい出来事とともに語られる
第22章 ここではラ・マンチャの中央部にあるモンテシーノスの洞穴で、勇敢なるドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャが首尾よくなしとげた大冒険が語られる
第23章 豪胆きわまるドン・キホーテがモンテシーノスの深い洞穴のなかで見たと語った驚嘆すべきことども、つまり、それがあまりにも壮大にして信じがたい話であるがゆえに偽りだと思われている冒険について
第24章 ここでは、この壮大な物語にとって無意味なように見えながら、そのまっとうな理解のためには不可欠である、凡百の 些事 が語られる
第26章 ここでは人形使いの愉快な冒険が続けられ、と同時に、そのほかの、まったくもって実に楽しいことが語られる
第27章 ここでは、まずペドロ親方とその占い猿の正体が明かされ、次いで、ドン・キホーテが予期したようにも、望んだようにも終ることのなかった驢馬の鳴きまねの冒険において、彼がこうむった災難が語られる
第28章 この章を読む人が、注意深く読めばその意味するところが分かるであろうと、ベネンヘーリが言っている 種々 のことについて
第29章 世に名高い、魔法の小船の冒険について
第30章 ドン・キホーテと麗しき女 狩人 とのあいだに起こったことについて
第31章 数多くの格別な事柄を扱う章
第32章 ドン・キホーテが自分を非難した聖職者に向けた反論、および、厳粛にして愉快なさまざまな出来事について
第33章 公爵夫人と侍女たちが、サンチョ・パンサを相手に交わした、読むにも記すにも値する、味わい深くも愉快な会話について
第34章 ここでは比類なきドゥルシネーア・デル・トボーソの魔法をいかにして解くべきか、その方法が明かされることにより、本書のなかでも最も名高い冒険のひとつが展開される
第35章 ここではひきつづき、ドン・キホーテに示されたドゥルシネーアの魔法の解き方が、そのほかの驚嘆すべき出来事とともに語られる
第36章 ここでは《苦悩の老女》の異名をもつ、トリファルディ伯爵夫人の、人の想像をこえた奇妙な冒険が語られ、それとともに、サンチョ・パンサがその妻テレサ・パンサに宛てた手紙が披露される
第37章 ここでは《苦悩の老女》の名高い冒険がひきつづき語られる
第28章 ここでは、《苦悩の老女》がみずからの不幸について物語ったことが語られる
第39章 ここではトリファルディ伯爵夫人が、その記憶に値する驚嘆すべき話を続ける
第40章 この冒険、およびこの記憶に値する物語にかかわりがあり必要でもある事柄について
第41章 木馬クラビレーニョの到来、および、長々と続いたこの冒険の結末について
第42章 島の領主として赴任するサンチョ・パンサにドン・キホーテが与えた忠告、および、よく考えぬかれたそのほかのことについて
第43章 ドン・キホーテがサンチョ・パンサに与えた、さらなる忠告について
第44章 サンチョ・パンサが統治すべき島へ案内された様子、および、公爵の城でドン・キホーテにふってわいた奇妙な冒険について
第45章 偉大なサンチョ・パンサが島に着任した 経緯 と、彼がどのように統治を始めたかについて
第46章 恋するアルティシドーラの求愛の過程にあって、ドン・キホーテがこうむった、鈴と猫からなる 戦慄 的な驚きに満ちた事件について
第47章 ここではサンチョの統治ぶりの続きが語られる
第48章 ドン・キホーテと公爵夫人お付きの老女ドニャ・ロドリーゲスとのあいだにもちあがったこと、および、書き記し、永遠の記憶にとどめるに値するそのほかの出来事について
第49章 島を巡視しているさなかに、サンチョ・パンサに起こったことについて
第51章 サンチョ・パンサの統治の展開、および、そのほかのなかなか愉快な事柄について
第52章 ここでは第二の《苦悩の老女》、もしくは《悲嘆の老女》、またの名を、ドニャ・ロドリーゲスと呼ばれる老女の冒険が語られる
第53章 サンチョ・パンサの統治の疲弊した終局とその最後について
第54章 この物語にかかわりがあって、ほかの物語とは関係のない事柄を扱う章
第55章 道中でサンチョの身に起こったこと、および、そのほかの 瞠目 すべき事柄について
第56章 老女ドニャ・ロドリーゲスの娘の名誉を守るために、ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャが従僕のトシーロスと交えた、前代未聞の、途方もない戦いについて
第57章 ドン・キホーテが公爵にいとま乞いをした次第、および、公爵夫人の侍女で、利発にしておちゃめな娘アルティシドーラとドン・キホーテとのあいだに起こったことを扱う章
第58章 ドン・キホーテの身に、 踵 を接して起こった数々の冒険を扱う章
第59章 ここではドン・キホーテの身に起こった、冒険とみなしうる奇妙な出来事が語られる
第60章 バルセローナへ向かう道中、ドン・キホーテに起こったことについて
第61章 バルセローナにやってきたドン・キホーテに起こったこと、ならびに、機知よりは真実味に富んでいるそのほかのことどもについて
第62章 魔法の首の冒険、および、語らずにすますわけにはいかない、そのほかの 些細 な出来事を扱う章
第63章 ガレー船の見物に際してサンチョ・パンサにふりかかった災難、および美しいモーロ娘の数奇な冒険について
第64章 それまでドン・キホーテの身に起こったいかなる出来事にもまして、彼に大きな苦痛を与えた冒険を扱う章
第65章 ここでは《銀月の騎士》の正体が明かされると同時に、ドン・グレゴリオの救出、および、そのほかの出来事が語られる
第66章 これを読む者には目に見え、人が読むのを聞く者にはその耳に入るであろうことどもを扱う章
第67章 ドン・キホーテが、約束した一年間が経過するまでのあいだ、羊飼いとなって田園生活をおくる決意を固めたこと、および、まことにもって楽しくもめでたき出来事について
第68章 ドン・キホーテの身にふりかかった豚の冒険について
第69章 この雄大な物語の全 をとおして、ドン・キホーテの身にふりかかった最も奇妙にして最も珍しい冒険について
第70章 この物語をはっきり理解するためには必要不可欠なことどもを、第69章にひきつづいて述べる章
第71章 サンチョとともに郷里の村へ帰る途中、ドン・キホーテに起こったことについて
第72章 ドン・キホーテとサンチョがどのようにして郷里の村に帰着したかについて
第73章 ドン・キホーテが故郷の村へ入るときに見た凶兆、および、この壮大な物語に彩りをそえると同時に、そこにさらなる 信憑性 を与えるそのほかの出来事について
第74章 ドン・キホーテが病いに倒れた次第、ならびに彼が口述した遺言書と彼の死について
「文庫3冊分」ということで、後編も長いですね(笑)
とはいえ、「冒険小説」なので、いったんストーリーに入れば、すいすい読みすすめていきます。
とくに牛島訳は、言葉づかいが一品なので、退屈することはありません。
セルバンテス『ドン・キホーテ・後編』で気になったトコ
以下、気になったトコをあげてみます。
サンチョのことわざ
前編では、付きそいの従士「サンチョ」は、ドン・キホーテにたいする〝ツッコミ役〟でした。
狂気にみちた主人の言動・行動にたいして、まっとうな言葉で、タダしていく役回りです。
いっぽう後編では、サンチョのキャラが、そんぶんに発揮されます。
ドン・キホーテの〝ドッキリ〟にまきこまれるかたちで、サンチョも被害をうけます。
その刺激により、サンチョがもつ、特性・特技が、おもてにあらわれるといったかんじです。
なかでもおもしろいのが、サンチョの表現、とくに「ことわざ」です。
後編になると、饒舌(じょうぜつ)になり、これでもかと「格言」を連発します。
一覧をあげると、こんなかんじ。
・警鐘を鳴らす奴は安全なところにいる
・愚か者も自分の家なら、他人の家にいる賢者より物が分かる
・水瓶が石に当たろうと、石が水瓶に当たろうと、ひどい目にあうのはいつでも水瓶
フレーズだけみても、おもしろいですよね。
これらを会話のなかで、ポンポンと発するわけです。
やり取りをきいてるだけでも、おもしろいです。
個人的にスキなのは、つぎの2つ。
・大事なのは誰から生まれたかじゃなく、誰といっしょに飯を食ったかだ(no.1709)
笑えるだけでなく、真理をついていて、ハッとさせられますよね。
とくに2つ目なんか、セルバンテスのやさしさが、にじみ出ていますね。
…
ドン・キホーテが「格式ばった表現」を連発するなら、サンチョは「身じかな表現」を発しまくる ─ 。
このあたりの対比・コントラストも、注目する点です。
公爵夫妻の悪ふざけ
後編では、狂気を利用されたドン・キホーテは、何度も〝ドッキリ〟をしかけられます。
その中心人物は、「ビリャエルモーサ公爵夫妻」です。
ふたりは、ドン・キホーテを「狂人」と知りつつ、いたずらをほどこします。
それにサンチョも、まきこまれていきます。
サンチョのムチ打ち
ドン・キホーテの想い姫「ドゥルシネーア」が、〝魔法〟によって「田舎むすめ」に変身された ─ 。
それを知った公爵夫妻は、魔術を解くための〝しかけ〟を思いつきます。
サンチョのムチ打ちです。
従士のお尻を、数千発たたくことで、ドゥルシネーアにかかる魔法が解ける ─ そう幽霊の騎士に語られるのです。
ラ・マンチャの光輝たる智勇兼備のドン・キホーテよ、比類なき美姫ドゥルシネーアが本来の姿を取りもどすためには汝の従者サンチョ・パンサが そのたくましき尻をむき出してそこに三千三百の鞭をみずから加え耐えがたき痛みに苦しむを要するなり。(2巻・no.2613)
〔……〕「冗談じゃねえ!」と、これを聞いてサンチョが言った。「三千どころか、おいらにとっちゃ、たった三回の 鞭打ちだって短剣で三突きされるようなものさね。そんな魔法解きなんぞ、くそっくらえだ! いったい、おいらの尻が魔法と何の関係があるんだね。(2巻・no.2621)
このシーン・やり取りは、エンタメとしてもおもしろいですよね(笑)
…
ほかにも、公爵夫妻は、
・ありもしない島の領主に「サンチョ」を就かせる
・ドン・キホーテに、ウデのたつ騎士と決闘させる
など、ドッキリ・いたずらを、しかけていきます。
こんなふうに後編では、ドン・キホーテが、みずからの「狂気」を発揮するというより、ワナにしかけられ、まわりがソレをたのしむ ─ そういう構図になっているわけです。
ドン・キホーテのめざめ
それもあってか、ドン・キホーテ自身は、みずからの狂気に、だんだんと気づいているフシがあります。
しかし、まわりがソレをよしとしない。
たとえば、地元の学生「サンソン」が、ドン・キホーテを目覚めさせようとします。
けれど、ドン・キホーテの狂気を楽しむ周囲は、「覚醒」をくい止めようとします。
この世に二人といないあんなに愉快な狂人を正気に戻そうとして、あなたが世間の人びとにかけた損害を神様がお赦しになりますように!ドン・キホーテが正気になって世にもたらすであろう利益なんぞ、彼の狂気沙汰がわれわれに与える喜びに比べたら物の数ではないってことが、あなたにはお分かりにならないんですか?(3巻・no.3679)
さらに、
〔……〕彼が治って正気になってしまったら、われわれは彼自身の愉快な言動を失うだけでなく、従士サンチョ・パンサのそれをも失うことになるからです。(3巻・no.3685)
とのべて、ふたりのやり取り=冒険を、終わらせないよう、必死になるわけです。
このあたりは、セルバンテスによる「メタ手法」 ─ 冒険の終わり=『ドン・キホーテ』という物語の終わり ─ が、うまく展開されています。
じっさい、目覚めつつある「ドン・キホーテ」の身に、新しい出来事は起きません。
地元に帰ってくるころには、なんの冒険も起きないわけです。
故郷の村へ向かった彼の身の上に、道中この真実の物語に記しておかねばならないようなことは、何ひとつ起こらなかった。(3巻・no.3695)
ドン・キホーテを楽しむ者たちがこそが、狂気にとらわれている
このようにして、冒険=物語は締めるセルバンテスですが、ひとつの注意書きを残しています。
それは、
というもの。
「ドン・キホーテ」のエピソードを記した、「シデ・ハメーテ」の口をかりて、教訓をそえているわけです。
シデ・ハメーテは、こう付け加えている ─ 人を愚弄する者たちも愚弄される者たちと同じく狂気にとらわれていると思う、現に、公爵夫妻は 一対 のばか者をからかい、もてあそぶのにあれほどまでの熱意を示しているのであってみれば、彼ら自身、ばか者と思われるところからほんの指幅二つと離れてはいないのだ。(3巻・no.4553)
めちゃくちゃ、するどい指摘ですよね。
こういう意見を書けるのが一流作家に値しますし、古典を読む〝だいごみ〟です。
おわりに
セルバンテス『ドン・キホーテ・後編』をみてきました。
近代以降の小説は、『ドン・キホーテ』から始まる、といわれます。
古典文学を知るうえでは、さけてとおれない作品です。
とはいえ、ムズかしくなく、たのしんで読めます。
気楽なキモチで、手にとってほしいと思います。
よければ、チェックしてみてください。
ではまた〜。